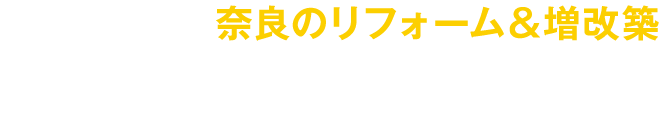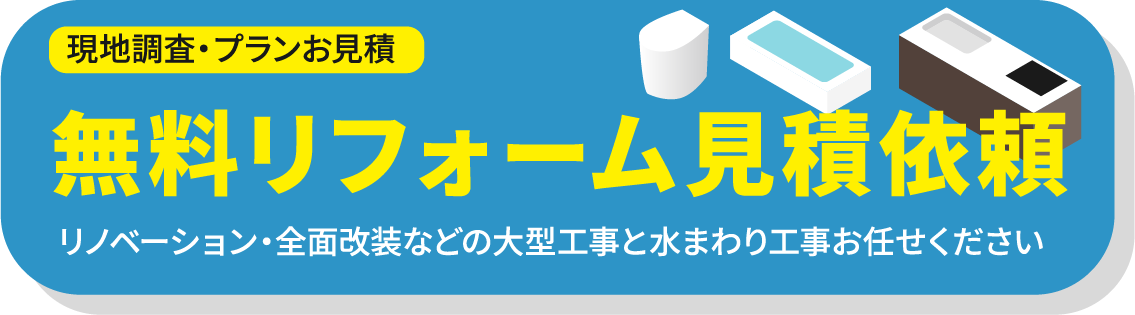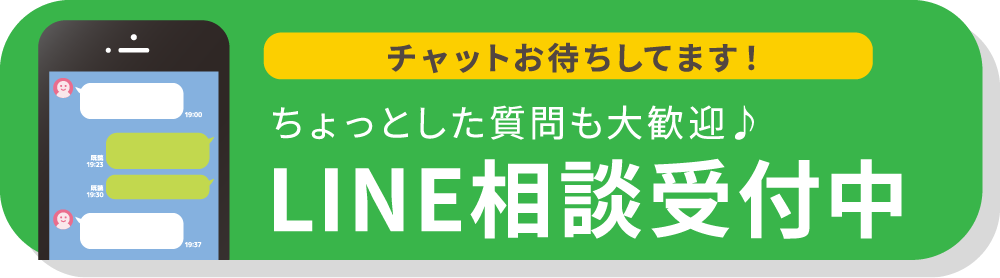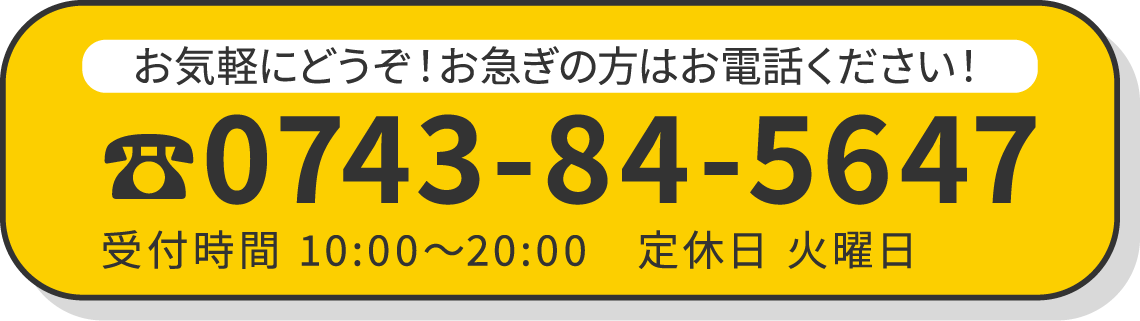再建築不可物件でもローンは組める?——通すための現実的ルートと手順
結論
「再建築不可=絶対にローン不可」ではありません。現実的な順番は次の4つです。
-
再建築“可”へ道筋をつけて通常の住宅ローンへ移行する
-
別担保を入れて住宅ローンや不動産担保ローンで組む
-
フリーローン/リフォームローン(無担保・有担保)を活用する
-
事業性(賃貸)として評価して資金化する
そもそも「再建築不可」とは?
敷地が“建築基準法上の道路”に十分に接していないなどの理由で、原則として建て替え許可が下りない土地・建物を指します。建て替えが難しい=市場流通性が低いと判断されがちで、金融機関が担保として取りづらいのがネックです。
住宅ローンが難しい理由(でも完全NGではない)
-
担保回収のリスクが高い:建替えできないと、万一の処分時に価値が伸びにくい。
-
適法性の不確実性:増改築や用途変更に法的ハードルがある。
-
とはいえ、適法化の見込みや別担保があれば、対応する金融機関はあります。
4つの資金ルートを詳しく
1) 再建築「可」へ格上げしてから借りる(最有力)
-
やること
-
道路種別・幅員・接道距離の現地/役所調査
-
セットバック(敷地の一部後退)で接道条件を満たせるか検討
-
但し書き許可(安全な通路計画などを整えて例外的に建築を認めてもらう制度)の可能性を役所と事前協議
-
-
金融機関への見せ方
-
事前協議の記録、工程表、見積を揃えて、**「許可取得後に本融資」**の条件で進める
-
-
メリット
-
適法化の道筋が見えると、通常の住宅ローンに近い条件へ寄せやすい
-
2) 別担保(共同担保・物上保証)で突破する
-
自宅や親族所有の不動産、保有マンションなどを追加担保に入れて、対象物件の担保不足を補う方法。
-
商品は、住宅ローン/有担保リフォームローン/不動産担保ローンなど。
-
現実に通りやすい策で、返済計画に無理がない範囲で担保余力がある人に向きます。
3) フリーローン/リフォームローンを併用
-
無担保型:上限は数百万円〜1,000万円程度、金利は高め、審査は比較的速い。
-
有担保型:上限を伸ばせるが審査はシビア、金利は下がる。
-
コツ:確認申請が不要な“修繕中心”(内装、配管更新、内窓、屋根の葺き替え等)に絞ると審査の印象が良い。
4) 事業性(賃貸)で評価してもらう
-
居住用ローンが難しくても、賃料収支で返済可能性を示すことで、アパートローン型の枠が使えるケースがあります。
-
必須資料:賃料査定、稼働計画、運営費、出口(長期保有か売却か)。
金融機関に提出すると“通りやすくなる”資料パッケージ
-
法規調査一式
-
道路台帳、敷地の測量図、接道条件の整理、役所との事前協議メモ(セットバック/但し書き許可の見込み)
-
-
工事の適法範囲の明記
-
今回は確認申請が不要な修繕中心なのか、許可取得前提の工事なのかを最初に宣言
-
-
工事計画の具体性
-
工程表、見積、図面、価値向上の根拠(断熱・防音・雨仕舞の改善など)
-
-
資金計画
-
自己資金、借入額、諸費用、許可取得後の借り換えシナリオ
-
-
出口戦略
-
居住継続/賃貸運用のどちらかを明記。賃貸なら賃料査定を添付
-
ケース別の“現実解”テンプレ
-
別担保を出せる
→ 追加担保+有担保ローンで調達 → 適法化後に住宅ローンへ借換 -
購入は現金、改修費だけ借りたい
→ 無担保リフォーム/フリーローンで改修費を捻出(窓・断熱・雨仕舞など体感が上がる部分を優先) -
賃貸運用が主目的
→ 事業性で打診。家賃収支と出口を明確に -
適法化の見込みが高い土地
→ 先にセットバック・通路整備などへ投資 → 許可取得後に通常ローンへ
工事の“やって良い/注意が必要”早見表
-
OKになりやすい(申請不要の範囲)
-
内装フル(床・壁・天井)、キッチン・浴室・トイレの入替、配管更新、内窓設置、既存開口の同等交換、屋根の葺替(構造をいじらない)
-
-
要注意/申請が絡む可能性
-
増築、耐力壁の撤去や移設、梁や柱に関わる変更、サンルーム増設、大きな用途変更
→ 設計者が**「確認申請不要の根拠メモ」**を付けると、金融機関の不安が和らぎます。
-
スケジュールの目安
-
一次調査(1~2週):法規・接道・既存図の収集
-
適法化の道筋づくり(2~6週):役所協議、セットバック/但し書きの可能性確認
-
資金ルートの当たりづけ(並行):別担保の有無、リフォームローン枠、事業性の選択
-
事前審査(1~2週):条件付承認を狙う
-
本申込~着工:中間・完了の写真と資料を残す
-
許可取得後の借換:金利の低い枠へ移行して月々負担を軽減
よくある質問(FAQ)
Q. 完全に無担保でも大きく借りられますか?
A. 無担保は上限が小さく金利が高め。改修費の一部に充て、将来の借換や別担保の投入も見据えるのが現実的です。
Q. まずは何から始める?
A. 1) 接道・法規の一次調査、2) 工事の適法範囲の確定、3) 資金ルートの選択、4) 審査用資料の整備。この順で進めると迷いません。
Q. どんな工事が審査で好印象?
A. 窓・断熱・雨仕舞・防音など、資産の保全性と体感を上げる工事。数字(省エネ改善、結露抑制、騒音低減など)の根拠を添えると◎。
まとめ(戦略の型)
-
第一優先は“適法化の道筋”。見込みがあるなら、そこに投資して通常ローンへ乗り換える前提で計画。
-
それが難しければ、別担保・リフォームローン・事業性を組み合わせて段階的に資金化。
-
金融機関には、調査→工事の適法性→価値向上の根拠→資金と出口をワンセットで提示するのが近道です。
奈良エリアのご相談は
ヨシケンホームでは、奈良県内の再建築不可案件について、
-
接道・適法化の事前調査と役所協議
-
確認申請の要否整理と工事計画の最適化
-
銀行提出用パッケージ(調査書・工程・図面・見積・写真)
までワンストップで伴走します。
「再建築不可だけど、直して住みたい/貸したい」という方は、所在地と想定工事、希望予算をお知らせください。通る可能性が高い資金ルートから具体案をご提案します。