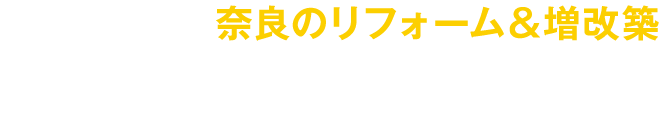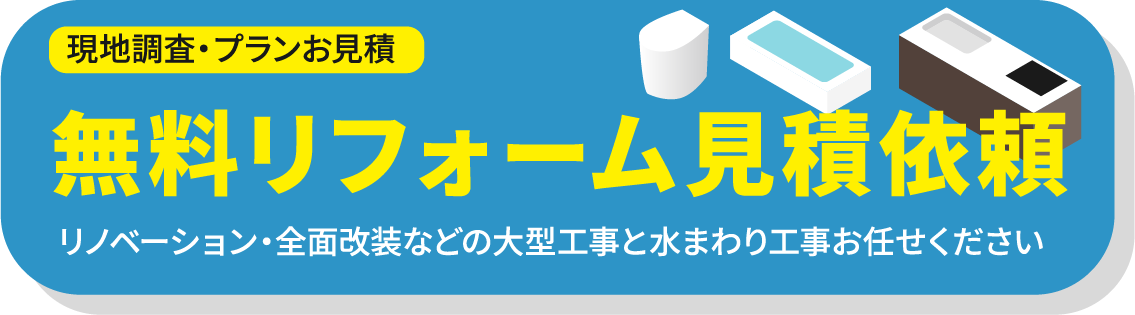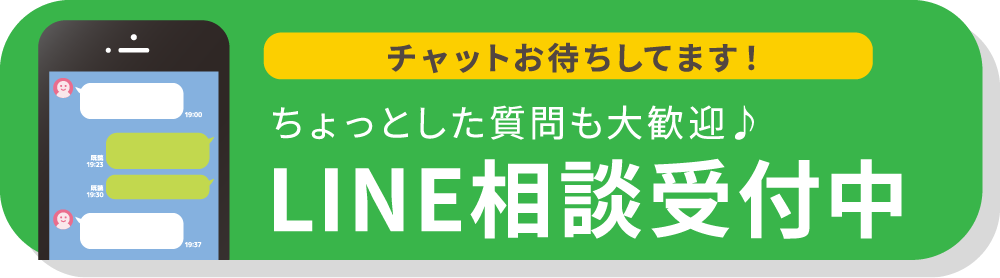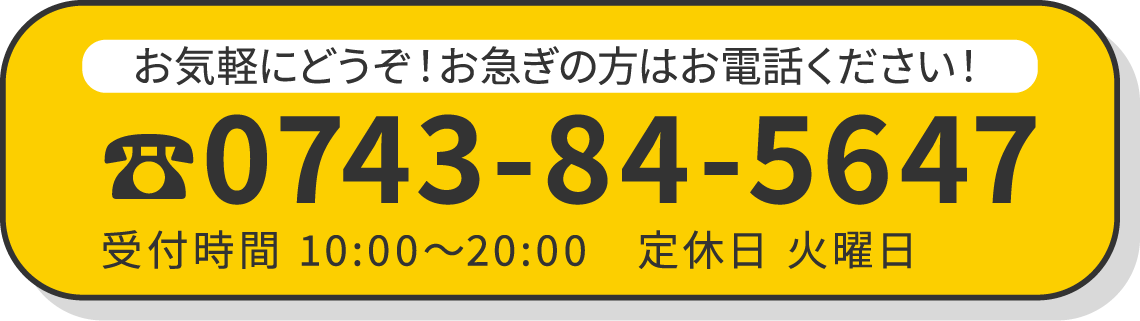王寺町の発展史と開発が進み始めた時期
生駒郡王寺町(奈良県王寺町)が「町として本格的な開発・都市化」が進み始めたのは、明治時代後期〜大正時代がきっかけで、その後、昭和の戦後〜高度経済成長期にかけて急速にベッドタウン化・宅地開発が進んでいきました。以下、王寺町がどう発展していったか、主な年代と開発の動き・背景を整理します。
王寺町の発展史と開発が進み始めた時期
王寺町の歴史資料等によると、町の発展には「鉄道の開通」が非常に大きな転換点でした。農村的な性格から、「交通と駅を中心とする町」へと変貌していきます。以下、時期を追って見ていきます。
| 年代 | 主な出来事・開発の動き |
|---|---|
| 明治23年(1890年) | 王寺〜奈良間の鉄道が開通し、王寺駅が設けられる。これにより久度(くど)地区あたりで駅前の交通利便性が飛躍的に向上。王寺町+2王寺町+2 |
| 明治24年(1891年) | 王寺〜高田間の大阪鉄道の開通。鉄道網の拡張が進む。王寺町+1 |
| 大正期 | 鉄道が増え、信貴生駒電気鉄道(近鉄生駒線など)なども開通。駅前商店街が発達、商業・住居の需要が増し、人口・世帯数が増加。王寺村が町制を施行して「王寺町」となる(大正15年=1926年2月11日)王寺町+3王寺町+3王寺町+3 |
| 昭和時代・戦後〜高度経済成長期 | 「西大和ニュータウン」の開発開始(昭和38年=1963年)。その後、宅地開発、駅周辺の商業施設整備、駅の橋上化、ニュータウン「美しヶ丘」などの住宅地造成、南駅前広場の整備など。高度成長期以降のベッドタウンとしての変貌。王寺町+2王寺町+2 |
「開発が進んだ」と言えるのは具体的にいつごろからか
上記より「本格的な開発が進み始めた」時点を具体的に挙げるとすれば:
-
鉄道の開通(明治23~24年頃、1890〜1892年) が大きな最初のきっかけ。これにより交通の便が劇的に改善され、商業施設や駅前集落の発展が始まります。王寺町+2王寺町+2
-
続いて 大正期(1910~1920年代) に入り、複数の鉄道線がつながることで王寺駅を中心とした「町としての体裁」が整い始め、1926年には町制を施行。王寺町+1
-
さらに、 昭和30~40年代以降(1960年代) に、ニュータウン開発などで住宅地造成が盛んになり、都市的な景観・人口構造に大きな変化が出始めた。王寺町+1
まとめ:開発が「何年くらい前」から進んでいるか
もし「町として開発が進んでいる状態」が始まった時期を「住宅地開発/都市機能が整い始めた頃」と定義するなら、
-
約130~140年前 = 明治時代後期(1890年ごろ)から、交通の利便性が底上げされて町が発展し始めた、ということができます。
-
また、「町制が施行された1926年」から「昭和30~40年代の宅地造成・ニュータウン開発」までは、街づくり・都市化が急速に進むフェーズ。