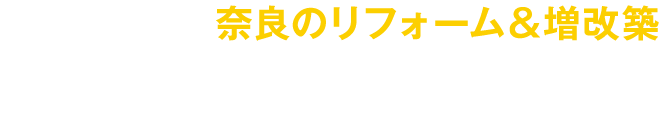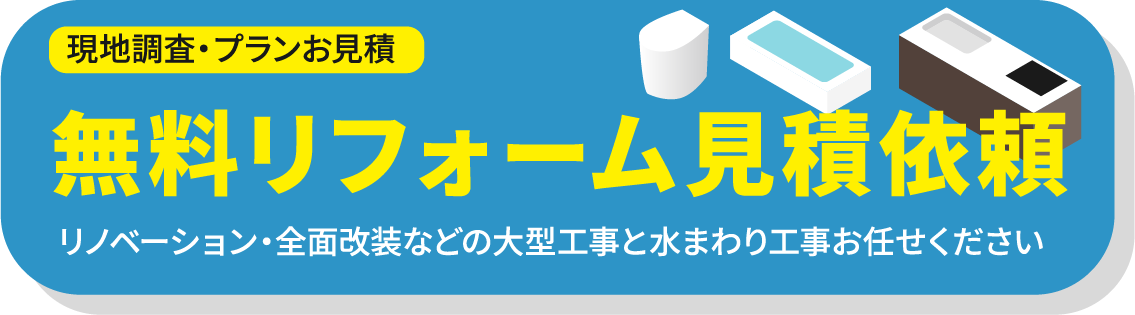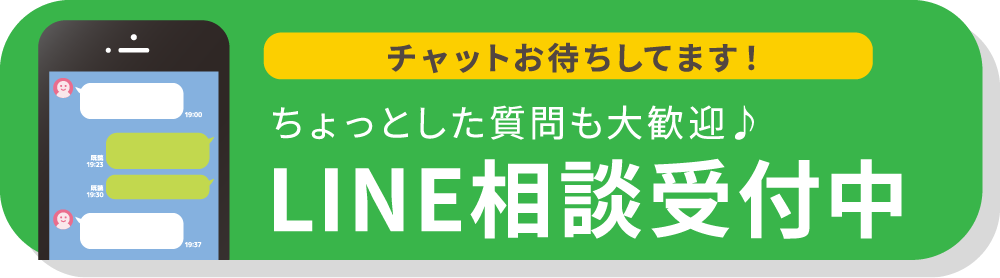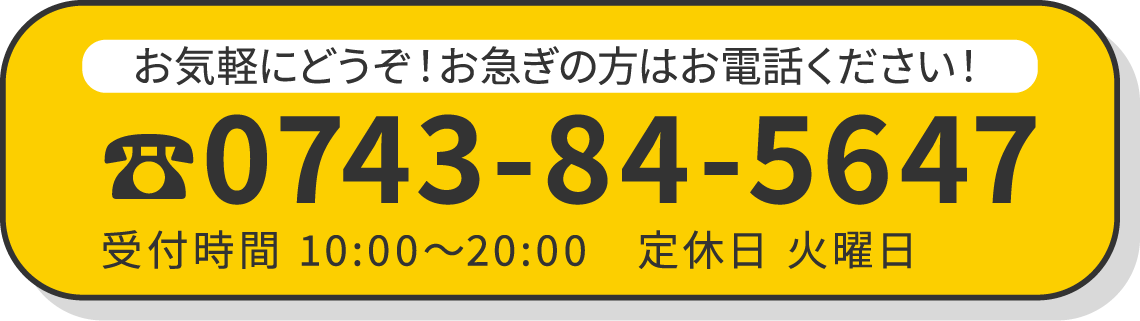郡山の地名の由来
1. 「郡山」の一般的な由来
-
**「郡(こおり)」+「山」**の組み合わせ
「郡(こおり)」とは、奈良時代に設けられた行政区画「郡(ぐん)」の古い呼び名です。
そこに「山」が組み合わさり、「郡に属する山」「郡の中心にある山」という意味で「郡山」と呼ばれるようになりました。 -
平安時代~鎌倉時代の文献にも「郡山」という表記が出てきます。
2. 福島県郡山市の場合
-
郡山市の由来は「郡の中心の山」という意味。
-
古代の安積郡(あさかぐん)の中心地にあったことから、郡の象徴となる山を「郡山」と呼び、それが地名になりました。
-
また、阿武隈川流域の扇状地に発展したことから「郡山盆地」の名も残っています。
3. 奈良県大和郡山市の場合
-
奈良の「郡山」は、戦国時代の 郡山城 に由来します。
-
城の築かれた場所が「郡(こおり)」と呼ばれていた地域で、その周囲に山や丘陵があったため「郡山」と呼ばれるようになりました。
-
豊臣秀長(秀吉の弟)が大和郡山城を大きく整備したことで、以降「郡山」という地名が全国に広く知られるようになりました。
4. 全国の「郡山」
-
奈良・福島以外にも、三重県伊賀市や山口県などに「郡山」という地名や山の名前が存在します。
-
多くは「郡の中心にあった山」や「郡の境界となる山」という意味で名付けられています。
まとめ
-
「郡山」という地名は、もともと 律令制の行政区画「郡(こおり)」と山の地形 を組み合わせたもの。
-
福島の郡山は「安積郡の中心の山」に由来。
-
奈良の大和郡山は「郡山城」に由来し、戦国大名によって広まった。
-
全国的にも「郡の象徴となる山」や「郡の境目の山」として名付けられるケースが多い