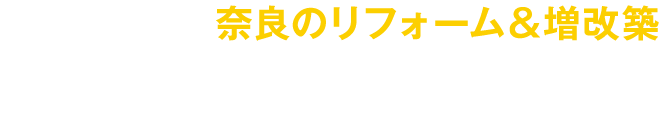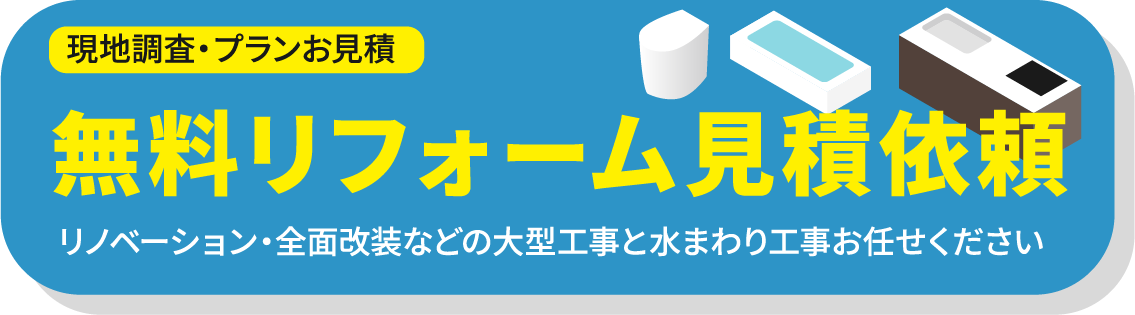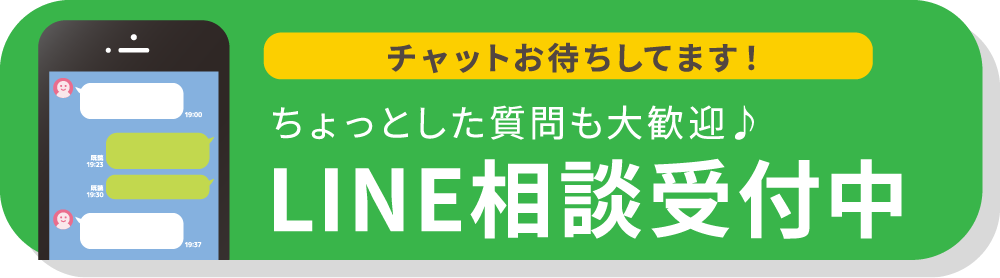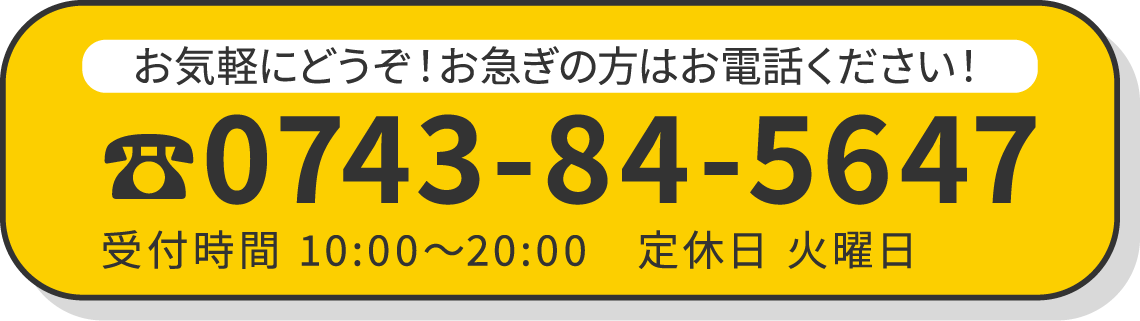「郡」という漢字の基本情報
「郡」という漢字の基本情報
-
音読み:グン
-
訓読み:こおり(古訓)、むら
-
部首:邑(おおざとへん/阝)
-
画数:10画
◆漢字の成り立ち
「郡」は、古代中国で「行政区画」を表すために生まれた字です。
-
左側の「君」=もともと統治者・指導者を意味
-
右側の「邑(おおざと)」=むら・集落
👉 「邑(むら)」を「君」が治めること → 「郡」という字になりました。
つまり、君主が支配する集落のまとまり を表した字です。
◆意味
「郡」には大きく分けて以下の意味があります。
-
行政区画
-
古代中国や日本で用いられた行政区分。
-
日本では「国 → 郡 → 郷(里)」という区分があった。
-
-
むら・集団
-
村落や群れを意味する。
-
例:「郡落(ぐんらく)=村々の集まり」
-
-
群と同義の意味
-
「郡」と「群」は音が同じで、意味も近く、しばしば通用。
-
「群衆」「郡集」といった表現で「集団」を表す。
-
◆日本における「郡」の使われ方
古代(律令制時代)
-
日本は 「国 → 郡 → 里(のち郷)」 という行政区分で統治。
-
「郡」は地方政治の単位で、中央から派遣された「郡司(ぐんじ)」が治めた。
-
奈良時代の『大宝律令』(701年)で正式に整備された。
中世〜近世
-
郡は荘園制や守護の支配の中で形骸化するも、地名として残る。
-
江戸時代には再び行政区画として使われることもあった。
近代(明治以降)
-
明治11年(1878):「郡区町村編制法」により、郡役所が置かれた。
-
しかし昭和に入り「郡役所」は廃止。行政単位としての郡は次第に形式的なものに。
-
現在は「郡」は地名に残るのみ(例:奈良県大和郡山市、群馬県群馬郡 など)。
◆「郡」と「群」の違い
-
郡(こおり/ぐん) … 行政区画・地名・村のまとまり
-
群(むれ/ぐん) … 動物や人の集まり
本来は別の字ですが、古代中国では通用し、日本でもしばしば混同されました。
◆「郡」の歴史を感じられる地名
-
大和郡山市(奈良県) … 大和国の「郡山」が由来。
-
福島県郡山市 … 陸奥国安積郡の中心にあったため「郡山」。
-
群馬県(ぐんま) … 郡と馬に由来する地名。
このように「郡」という字は、日本各地の地名に色濃く残っており、古代の行政制度の名残を今に伝えています。
◆まとめ
「郡」という漢字は、君主(君)が邑(むら)を治めることから生まれた字で、古代の行政区画を示す重要な用語でした。日本では律令制下の地方制度に使われ、その後も地名として数多く残っています。
つまり「郡山」という名字や地名は、郡の中心となる山や象徴的な場所 を意味し、その土地の歴史を今に伝えるものなのです。